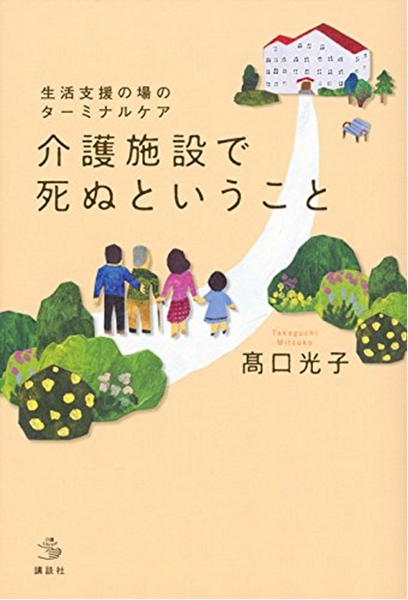 ■書名:生活支援の場のターミナルケア 介護施設で死ぬということ
■書名:生活支援の場のターミナルケア 介護施設で死ぬということ
■著者:髙口 光子
■出版社:講談社
■発行年月:2016年11月
>>『生活支援の場のターミナルケア 介護施設で死ぬということ』の購入はこちら
介護求人ナビは全国の介護・福祉・医療の求人を掲載している業界最大級の転職サイトです。
介護職・ヘルパーはもちろん、ケアマネジャーやサービス提供責任者など介護に関わる様々な職種を対象に、全国の介護施設・介護事業所の正社員、パート・アルバイトの求人を掲載中。
希望の勤務地、雇用形態、サービス・施設形態、休日、待遇、アクセス、資格、経験などこだわりの条件からあなたにぴったりのお仕事が探せます。転職支援サービスに登録すると、専門のキャリアアドバイザーから求人の紹介、履歴書の添削、面接のサポートを受けることもできます。
介護・福祉・医療業界の転職、就職、パート・アルバイト先探しに、ぜひ介護求人ナビをご活用ください。
■希望の職種から求人を探す
介護求人ナビは全国の介護・福祉・医療の求人を掲載している業界最大級の転職サイトです。
介護職・ヘルパーはもちろん、ケアマネジャーやサービス提供責任者など介護に関わる様々な職種を対象に、全国の介護施設・介護事業所の正社員、パート・アルバイトの求人を掲載中。
希望の勤務地、雇用形態、サービス・施設形態、休日、待遇、アクセス、資格、経験などこだわりの条件からあなたにぴったりのお仕事が探せます。転職支援サービスに登録すると、専門のキャリアアドバイザーから求人の紹介、履歴書の添削、面接のサポートを受けることもできます。
介護・福祉・医療業界の転職、就職、パート・アルバイト先探しに、ぜひ介護求人ナビをご活用ください。
■希望の職種から求人を探す